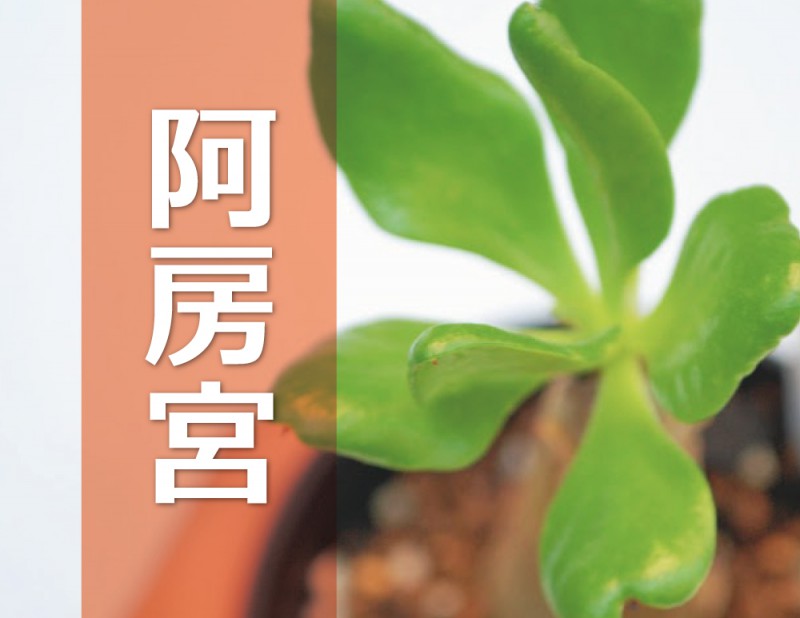春秋型の多肉植物ばかり育てていたので、あまり馴染みのない「冬型種」の生育期…。
実際、難しく思う方も少なくないのではありませんか?
僕もそのうちの1人。
街の園芸店やホームセンターに並ぶ多肉植物はベンケイソウ科をはじめとする「春秋型」が多いので、冬型種の栽培に失敗してしまうこともしばしば…。
とくに「珍奇植物」の影響で冬型コーデックスの流通も増加しています。
極めつけは、他のコーデックスには「夏型」が多いのでついつい混同、終いには枯らしてしまう悲劇があるやもしれません…。
僕の勉強のためにも、改めて振り返っておこうと思います。
「冬型」種のコーデックスはどう栽培するんだろう?
はじめての冬型コーデックス
今年の2月。
とあるオフ会に参加し、趣味家の方から破格の安さで譲ってもらったコーデックス。

名札には「阿房宮」とあります。
葉も縮れかけ、もしやと調べるとやっぱり冬型のコーデックス「チレコドン・パニクラータス(Tylecodon paniculatus)」。
ついこの間まで、リトープスが冬型であることも知らず夏の間にバンバン水をあげていた無知な野郎のワタクシ。
いきなり冬型のコーデックス様を扱うことができるのか…。
いわば小学2年生が因数分解を学ぶように、基礎も何もないから分からない。
慌てて多肉本をひっくり返し「冬型」の多肉植物についておさらいしたのです。
「冬型種」とは何か
多肉植物には「春秋型」「夏型」「冬型」の3つの生育期があります。
代表的なもので、
- 春秋型
セダム
エケベリア
ハオルチア - 夏型
アデニウム
カランコエ「月兎耳」
アロエ・ベラ - 冬型
チレコドン
リトープス
アフリカ亀甲竜
など。
このうち、クラッスラの中にも夏型と春秋型があったりと、植物の種類によって変わることも1。
冬型種の生育サイクルをざっくりと書くと、気温の低くなる秋ごろから生長をはじめ、気温がさらに低くなると生育を止めます。
そして春になるとまた少し生長を始め、夏には完全休眠…を繰り返すのです。
この「阿房宮」の場合、休眠に入ったかどうかの判断が非常にわかりやすくて、夏に入ると葉を全て落とすのです。
僕は葉が残り1枚になったときに「休眠した」と判断しました。
夏の水遣りは「ダメ、ゼッタイ。」
そうそう。
冬型種の場合、休眠中の夏には絶対に水を遣ってはいけいないと言われます。
他の多肉植物も真夏の間には断水しますが、この夏「阿房宮」には一滴も水を与えませんでした。
これが結構恐ろしくて、心を鬼にしないと不安で仕方がありません。
いつも思うのですが、インパチェンスやアジアンタムなど水を大変に喰らう植物と、夏の間は断水させる植物を一緒に育てられる人ってスゴイと思います。
萎れていく植物に水をあげようとするのは植物好きの「情」であり、「本能」ですが、そこをぐっと理性で抑えて判断できるのは相当な趣味家だと思います2。

ちなみに休眠中の置き場所は、雨にかからない戸外で、真昼の日光を遮断できる場所に置いていました。
もっと言えば、目に入るとどうしても気になってしまうので、故意に目に入らない場所へ隠しました(笑)。
意識的に「阿房宮」の存在を忘れたのです…!
結果、9月には新芽が出始め、ようやく水を与えることができたのです。

それと同時に、「冬型コーデックス」の緊張から解放されたのは言うまでもありません(笑)。
良かった…(*´▽`*)。
「冬型だから寒さに強い」ワケではない
まずは夏を越せたので安心したものの、今度は冬。
いくら冬型とはいえ、基本的な生育温度は5℃~20℃を保つ必要があるそうです。
冬型種
引用元:多肉植物 (NHK趣味の園芸 よくわかる栽培12か月)
生育適温は5~20℃です。日本では冬に生育します。最低気温が一定以上になると、生育をはじめますが、寒さに強いわけではありません。
(中略)
部屋を閉めきって高温にすると、生育期の冬でも休眠・生育停止してしまいます。
雪が降るような温度のもとで管理してしまえば、当然、枯れる恐れがあるということ。
「冬型って言うくらいだから、冬は外に出しておいてもいいんでしょ?」ということにはならないみたいです。
気になる冬の水やり
ここで問題になるのは水遣りです。
基本的に「春秋型」の栽培に慣れた僕は、冬も断水するという固定観念に縛られています。
では、冬の間の水やりはどのように施せばいいのでしょうか。
サボテン相談室の羽兼直行氏の著書には、
室内に取り込む。水やりは1~3週に1回
冬は室内で栽培します。
(中略)
冬型種といっても、真冬は生長が鈍ります。水やりは控えめにしましょう。ただし、暖房した部屋は湿度が低く、意外と鉢土の乾きも早くなることがあるので、よく観察して水やりをしてください。
とあります。
また「表土が乾いたらたっぷりと与える」と記述された書籍もあり、回数についての表記はまちまち。
ただし、部屋に取り込むこと、暖房の効いた室内では湿度が下がっていることなどから、観察しながら適宜水やりをする必要があるとのこと。
解法が分かれば怖くない
冒頭で小学2年生が因数分解を学ぶと書きましたが、小学2年生が因数分解を解けない訳ではありません。
解法が分かれば誰でも解けるようになるのです。
つまり、冬型コーデックスに極度に恐れをなしていた僕ですが、栽培方法を知って安心できたのも事実。

デッド・オア・アライブというか、オノレの判断で枯らすか枯らさないかが左右される園芸の世界。
枯らさないようにするためには必要な情報をしっかり得て、それを実践すること。
ワリと教科書通りに行動すれば間違いありません。
独創性のない僕でも、情報力と行動力さえあれば応えてくれるのが嬉しいのです。
この調子でこの冬も乗り越えていきたい!頑張ろう「阿房宮」!!